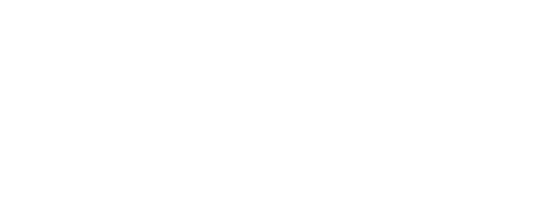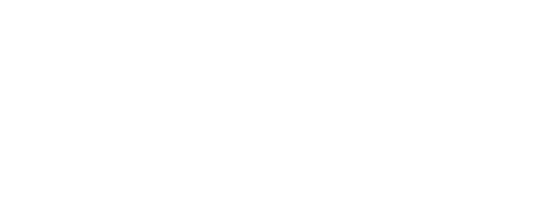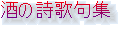戦地別れの酒詩
詩人の大木惇夫と石原吉郎の戦場に置かれたときの酒詩を編纂しました。大木惇夫氏は明治28年生まれで、太平洋戦中下に南方に派遣されたときに詠った「戦友別盃の歌」は,古関裕而作曲の戦時歌謡「海を征く歌」となって多くの青年たちに愛唱されたそうです。
私が大木氏を知ったのは、古今東西の酒の詩歌を編纂されたおよそ50年前の書を発見してからで、氏の酒歌への愛着はすごいものがあります。
一方、石原吉郎氏は大正4年生まれで、東京外語卒、シベリアに8年、強制収容された経験をもちます。青春を喪失したその極限における体験から詠まれる詩には、情緒を否定したような非常な世界が表されています。 由 無
参考:大木惇夫編著『酒の詩歌十二ヶ月』(経済往来社)
現代詩文庫『石原吉郎詩集』(思潮社)
酒がのみたい夜は
酒だけでない
未来へも罪障へも
口をつけたいのだ
日のあけくれ
うずくまる腰や
夕ぐれとともにしずむ肩
酒がのみたいやつを
しっかりと砲座に据え
行動をその片側へ
たきぎのように一挙に積みあげる
夜がこないと
いうことの意味だ
酒がのみたい夜はそれだけでも
時刻は巨きな
枡のようだ
血の出るほど打たれた頬が
そこでも ここでも
まだほてっているのに
林立するうなじばかりが
まっさおな夜明けを
まちのぞむのだ
酒がのみたい夜は
青銅の指がたまねぎを剥き
着物のように着る夜も
ぬぐ夜も
工兵のようにふしあわせに
真夜中の大地を掘りかえして
夜明けは だれの
ぶどうのひとふさだ
言うなかれ、君よ、わかれを、
世の常を、また生き死にを、
海ばらのはるけき果てに
今やはた何をか言はむ、
熱き血を奉ぐる者の
大いなる胸を叩けよ、
満月を盃にくだきて
暫し、ただ、酔ひて勢へよ、
わが征くはバタビアの街、
君はよくバンドンを、
この夕べ相離るとも
かがやかし南十字を
いつの夜か、また共に見む、
言ふなかれ、君よ、わかれを、
見よ、空と水うつるところ
黙々と雲は行き雲は行けるを。
石原吉郎
1915年(大正4年)伊豆生まれ。東京外語卒。1945年ソ連軍に抑留され重労働25年の判決を受ける。53年帰還後、詩作を開始。64年詩集『サンチョ・パンサの帰郷』でH氏賞を受賞。
大木惇夫「戦友別杯の歌」
俳句 淀風庵
大木惇夫
明治1895年(明治28年)広島市生まれ。 戦争中は南方に派遣され軍歌を作っており、戦後、戦争賛美者として ジャーナリズムから無視される。
漢詩や欧州の詩人の詩を多く訳している。1977年 (昭和52年)没。
藍いろに暮れて、灯して
酒みづき 飲みて溺れて
酔ひ痴れてわれはあるとも、
ここはジャワ、バタビヤの街
オランダの酒場と思へば、
醒めぎはの何ぞはかなき。
ほとほとに恋ほし、はるけし、
さびしさを消たむと思ひて
更に乾す一杯の酒、
その酒もくろきにあらぬ
外国の理の酒、
更に飲み、飲みて果つとも
いかにせむ、こころの底ゆ
吾は酔はなくに。
大木惇夫「オランダ酒場にて」
石原吉郎「酒が飲みたい夜」