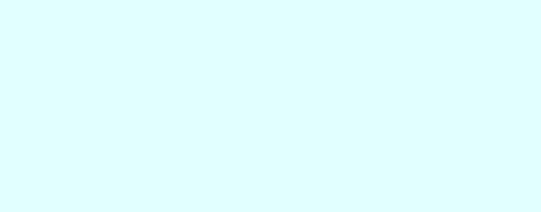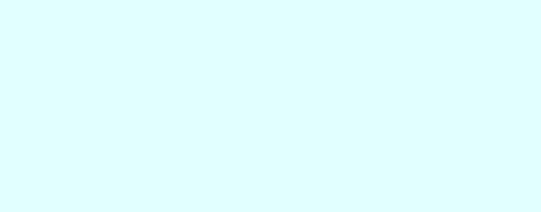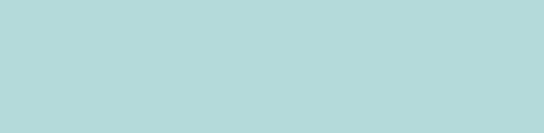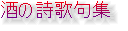吉井勇・酒ほがひ
酒と愛欲の青春を詠って、明治末の青年を魅了した吉井勇の処女歌集
『酒ほがひ』(明治43年)、そして土佐の草庵に転じた頃の歌“あぐら酒”(昭和14年出版歌集『天彦』収載)を紹介します。これらの作品には彼のひたむきで直裁的な感情の表現を感じ取れます。
なお、酒を詠いこんだ歌はこのほかに数多あり、また「かにかくに祇園は恋し寝るときも枕の下を水のながるる」(『祇園歌集』)のように紅灯の巷に材を取った歌でも目立った存在で、牧水の短歌同様にそこはかとなく侘しさが伝わってきます。 由 無
酒ほがひ
少女云うこの人なりき酒甕(かめ)に凭りて眠るを常なりしひと
酒びたり二十四時を酔狂に送らむとしてあやまちしかな
覚めし吾酔ひ痴れし吾今日もまた相争ひてねむりかねつも
酒の国わかうどならばやと練り来貴人(うまびと)ならばもそろと練り来
かの君の酒に酔ひけるよ人は知らじな酒のかなしみ
酒みづきさなよろぼひそ躓かば魂を落さむさなよろぼひそ
諾とも云ひ否とも云へるまどはしき答を聴きて酒に往きける
杯のなかより君の声としてあはれと云うをおどろきて聴く
わが胸の鼓のひびきたうたらりたうたうたらり酔へば楽しき
眼さきに蒼蝿と見しは獅子なりきものあやまちしとろとろの目よ
君なくばかかる乱酔なからむとよしなき君を恨みぬるかな
かかる世に酒に酔はずて何よけむあはれ空しき恒河沙びとよ
酔びとよかなしき声に何うたふ酔ふべき身をば嘆けとうたふ
さな酔ひそ身を傷(やぶ)らむと君云はず酒を飲めどもさびしきかなや
酒を見ていかにせましと考ふるまに百年千年(ももとせちとせ)過ぎなむ
恋がたき挑むと云はれおどろきし弱き男も酒をたうべぬ
な恋ひそ市の巷に酔ひ痴れてたんなたりやときたる男を
甕越(みかごし)にもの云うひとの濡髪をただ見てあるにこころよろしき
博打たずうま酒酌まず汝等みな日をいただけど愚かなるかな
かなしみて破らずという大いなる心を持たずかなしみて破る
事わかず疑ひしげくなる時は壺の口より酒にもの問ふ
覆へす酒の甕より出でたるは誰にかくせし誰の艶書ぞ
弱きかな恋に敗けては酒肆(さかみせ)に走りゆくこといくたびかする
酒に酔ひ忘れ得るほどあはれにも小さくはかなきわれの愁か
あれ庭に蜥蜴あそぶをながめつつ焼酎酌みて端居すわれは
われもまたおぞのみやびを妹の云う恨言(かごと)も聴かで酒をこそ酌む
何ごともあきらめ果ててすがすがし土佐焼酎の舌ざはりかも
縁先に大あぐらゐてぎやまんの杯取れば思ふことなし
寂しさの極まるときやあぐらゐて酒をこそ酌めせんすべ知らに
をりをりは悔しと思ふことありてはだらはだらに白む鬢はや
心なほ壮んに眉をあぐることなきにしもあらず酔はしめたまへ
焼酎を胸にそそぎて男の子われはづかに心遣るをとがむな
焼酎を酌むあぐら居の縁に聴く遠いかづちの音はよろしも
わびずみの夕さびしく縁にゐて焼酎酌みぬ友なしにして
うつそみのはらわたに染むうまし酒焼酎を盛るぎやまんぞこれ
たそがれの縁に端居し酒を酌み蜥蜴あそぶを見つつ飽かなく
このままに朽つるわが身と思はねばあぐらゐしつつざれ言もいふ
酒ほがひ(2)
(1)
あぐら酒