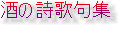吉井勇・酒ほがひ
吉井勇は60歳を過ぎて孤独な土佐の草庵を抜け出し、人生流転の生活に終止符を打ちましたが、草庵時代の心境や京へ移った後を詠った歌集『天彦』を発表しました。その中から「寂しければ」を中心に、孤独な日々の慰みとして酒に焦がれた気持ちをしたためた歌を紹介します。 由 無
参考:『吉井勇歌集』(岩波文庫)
寂しければ
寂しければ酒をこそ酌めまたしても苦きを啜り酔泣きをせむ
寂しければ山酒酌めどなぐさますただしらじらと酔ひつつぞ居る
寂しければ或る日は酔ひて道の辺の石の地蔵に酒たてまつる
寂しければ酔ひて手を拍ち唄うたう今戸益喜の顔もおもしろ
寂しければ酒麻呂いかに新醸り香やいかになど思はるるかな
寂しければ垣に馬酔木を植えにけり棄て酒あらばここに灌がむ
寂しければ昨夜のなごりの酒おくび吐きつつぞ飲む石楠の茶を
寂しければ爐に酒を煮て今日もあり韮山山峡冬深みつつ
寂しければはやくも丑に起くるなり夜半の爐酒のなつかしきまま
寂しければ催馬楽めきしざれ歌も酔のまぎれにうたひさふらふ
寂しければ酒ほがひせむこよひかも彦山天狗あらはれて来よ
山ごもり濁り酒酌みあるもよしむかしの夢を見てあるもよし
ひさかたの月の夜なれば酒酌まむ益喜も酔ひぬわれも酔はまし
月夜よしこよひの酒のさかなには生椎茸を焼くべかりけり
あばれ酒憤り酒幾とせかつづきしのちの寂しさかこれ
夜ふかく寝酒を酌むと酒煮れど寂しきかもよ妹の訪ひ来ぬ
酒にがくなりてさびしやただひとり島邊の宿に蛸の飯食す
下ごころ寂しきものを腹かかへゑらぎ笑へり酒みづきつつ
太腹をゆらす揺すりて酔ひにけり竹原酒の樽となるべう
おもしろき酒ほがひかな逞ましき肩そびやかし頼とこそ告れ
冬空を見つつ冷たき酒酌むをせめて怒りのやりばとぞする
うつそみの命消ぬがにあるものをせめては夜毎酒に酔はしめ
うつそみも心も崩れゆくごとしいともあやふき酔びとかこれ
冷酒を酌めば韮生の山峡の夜のさまなど思はるるかな
人問はば土佐阿闇梨ともなりも得でなほ酒みづくわれとこたへよ
いきどほろしく酒は酌めども然は酔はず冷やかに笑むわれとなりき
なほ胸にすこし悔しき思ひありて昨夜の残りの酒を煮むとす
わびずみの夜ごとの酒をたのしみてよしなきことは嘆かずもあれ
もの書かむこころ起こりて墨磨りぬわび居さびしき酔のまぎれに
しみじみと爐酒を恋ふるこころもて韮生山路をたどり来にけり
たたかひに死にたるひとの墓のまへゆきずりわれも酒をたてまつる
しばらくは半跏組み目閉ぢぬ爐酒のにほひいまもただよふ
酒あまり飲むなと吾子の文にありこの杯をいかにかはせむ
太腹を撫でつつなげくあぐら居のあたら男の子に酒を酌ましめ
杯をしづかに伏せぬ思ふこと胸の奥処に触れて来ぬれば
酒のなき夕餉さびしもいろ黒の麦飯食してはやくねむらむ
もの読むを楽しとすれど夜を寒みただいささかの酒欲りにけり
都邊は風あらあらしわが友よ酒は酌むとも深酔なせそ(久保田万太郎へ)
伽藍の香のみなぎるなかにあぐらゐて酒を酌みしもいまは昔か
(2)
身辺の冬…ほか
吉井勇
明治19年、東京生まれ、早稲田大学中退、耽美派文学の一翼として、歌業のほかに戯曲、小説、歌謡(「ゴンドラの唄」の作詞など)多彩な活動、昭和35年永眠
俳句 淀風庵