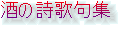一休の風狂酒詩
室町時代の臨済系禅僧・一休宗純は、後の江戸時代に頓知の小僧として敬愛される存在となりますが、長じては酒屋や遊里に遊ぶなど僧にはあるまじき破戒三昧の生活を送っています。
江戸後期の曹洞宗系の禅僧・良寛も子供と遊んだり酒を好んで、庶民に親しまれていますが、その無頓着さや風来ぶりと、詩に秀でている点、そして老年になって女性を恋する点でも二人には共通性があります。
一休師には寺僧の退廃ぶりを批判した詩とともに、自らの放蕩ぶりを露にした詩もあります。その中から酒を詠んだ詩を探しました。なお師は、晩年、盲目の森女と同棲したと言われており、小僧のころから生涯にわたり人々をドキリとさせてくれますね。最終章は、京の名刹・大徳寺の住持に迎えられ、高僧として名を連ねることになります。 由 無
参考:富士正晴『一休』 二橋進編訳『一休狂雲集』
水上勉『一休を歩く』 市川白弦『一休』
住庵十日意忙々 庵住み十日でうずうずしたわ
脚下紅糸線甚長 俗世の誘惑はなはだつよい
他日君来如問我 いつかお出でて もしさがすなら
魚行酒肆又淫坊 魚屋、居酒屋、または女郎屋へ
風狂々客起狂風 風狂の狂客 狂風を起し
来往淫坊酒肆中 女郎屋 酒屋の中をうろうろ
具眼衲僧誰一拶 眼のある坊主よ 何とか言えよ
画南画北画西東 南を区切り、北、西東、どこへも行かすんじゃない
寒哦秀句在三冬 さびしき秀句は冬三月
酔後樽前盃酒重 酔うて樽の前 飲んで飲む
枕上十年無夜雨 ねても十年 連れがない
月沈長楽五更鐘 月は沈んで長楽寺 五更の鐘をついている
在僧目白在妻青 坊主がおれば白目むく 妻が相手にゃ優しい目
対客唯言我薄情 客に対し唯いうは わしゃ薄情だとそれだけだ
花前酌尽一樽酒 妻まえにして飲みつくす一樽の酒
半酔夜深猶半醒 半酔い夜ふけてまだ半醒よ
酔郷藁屋我家山 酔えば藁屋もわが故郷
燭影三更対玉顔 火ともし深夜美人に向う
夜雨無愁歌吹海 夜の雨 愁いもあらぬ 花の街
○娥須是堕人間 月の精 人の世界に堕ちて来よ ○:恒の偏が女
風外松杉乱入雲 風もないのに外の松杉乱れ 官に近づくこれ何じゃ
諸方動衆又驚群 諸方の寺々大衆動員 坊主さわがしこれ何か
人境機関吾不会 人事のからくり わしゃわからん
濁醪一盞酔醺々 どぶろくの一盃 酔うてごきげん
創作句集
富士正晴氏の意訳による
一休宗純
1394〜1481年、後小松天皇の側室の子として生まれ、6歳で出家。飢餓と争乱の中、人間的な自由禅を求めて各地の寺を渡り歩く。81歳のとき京都の臨在系大徳寺の住職に迎えられる。