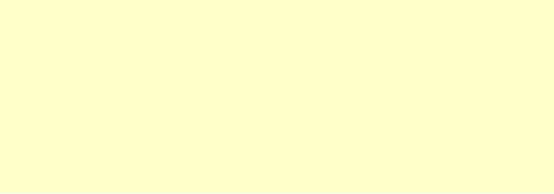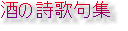アブ・ヌワース酒色詩
アブー・ヌワースは8〜9世紀にかけて、ペルシャの影響もあって科学文化の花開いたイスラム帝国・アッバース朝時代にバクダードを中心に活躍した詩人です。従来の厳しい音韻規則に縛られずに、平坦で機知に富んだ彼の詩は現在も広くアラブ世界で愛誦されているそうです。残された千余りの詩の中でも、飲酒詩は戒律厳しいイスラム世界においては異端ですが、それだけに妖しい光を放つのではないでしょうか。
奔放闊達な表現で、ひたすら酒色を讃美する詩風や、酒場に入り浸り投獄されたりの素行からみて、李白やオマル・ハイヤームほどに哲学的境地はなく、俗物的に快楽に耽溺する人物像が伺えます。
なお、今もバグダードにアブー・ヌワース通りや酒杯を手にしたアブ・ヌワースの像があります。 由 無
参考:塙治夫訳『アラブ飲酒詩選』(岩波文庫)
朝 酒
夜明け前、朝酒を思い浮かべて心が安らいだが、一番鶏のうるさい叫びにはうんざりした。
・・・・・
朝になったら、早速朝酒をやり給え。ぐずぐずして酒を出し惜しみしてはならない。
朝酒は酔漢の頭をすっきりさせるもの、朝には手が素早く盃にのびてゆく。
そこに快楽の販路で、話し上手の仲間がいれば、彼のざれ言と戯れは心の糧となる。
闇夜の酒
闇夜、私は酒家に駱駝の荷を下ろした、そこに住み着く人のように。
私は言った。「生の酒を注いでくれ。水を混ぜたら、灯火のように輝く酒を」
親父は言った。「十年物がありますよ」私は愛を語るようにいった。
「味見させてくれ、そうであることを知るために」彼は泡立つ酒をぐいと出した。・・・・・
私は言った。「酒屋よ、お前の言うとおりだ。これは私が長く必要とする酒だ」
二つの陶酔
ライラーやヒンドのために一喜一憂するのはよし給え。薔薇を愛でつつ薔薇のような赤い酒を飲み給え。
盃から酒が喉に流れ落ちると、目と頬をたっぷりと紅に染めてくれる。
酒はルビー、盃は真珠、それをもつのはすらりとした遊び女のたなごころ。
彼女は酒を目から注ぎ、手から注ぎ、私は二度酔わずにいられない。
年老いた酒
ルビーのように赤い酒をグラスに注ぐと、私の手は今にも血がにじみそうだ。
甕の中で年老いた酒の何と美しいことか、関節や骨にしみわたる味の何とよいことか。
酒は糞真面目な人の理性に言い寄り心も、知能もとろかしてしまう。
酒は人の悩みを少しずつ除いてくれる、どれほど悩みがたまっていようとも。
酒は機知名人を気前よくし、一文無しを金持ちにさせてくれる。
また私は知っている、酒は体によいことを。雨が水に乾いた自然によい以上に。